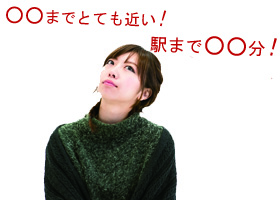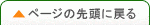住宅に関する基礎知識
住宅ローン金利比較(新規・借り換えでの適用金利)
| 名称 | 表面金利(%) | 優 遇 条 件 |
保証料 | 事務 手数料 |
繰上返済 手数料 (変動) |
来店 | 疾 病 保 険 |
詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動 金利 |
10年 金利 |
20年 金利 |
||||||||
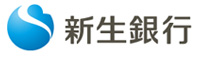 新生銀行 |
0.45 | 0.75 | 0.95 | なし ○ | なし ○ | ②契約事務手数料/保証料 借入金額がいくらでも55,000円~ ※ただし、変動金利<変動フォーカス>0.45%のみ、借入金額×2.2% | 無料 |
不要 ○ |
あり ○ | 詳細 |
 住信SBIネット銀行 |
0.380 | 0.58 | 1.21 | なし ○ | なし ○ | 借入額の2.20%(税込) | 33,000円(税込) |
不要 ○ |
あり ○ | 詳細 |
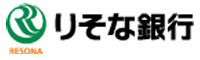 りそな銀行 ※2020年3月 適用金利 |
0.429 | 0.60 | 0.90 | あり × | なし ○ | 33,000円(税込)+お借入金額×2.2% | 無料~33,000円(税込) |
不要 ○ |
あり ○ | 詳細 |
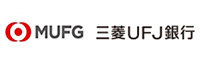 三菱UFJ銀行 |
0.475 | 0.64 | 2.84~2.99 | あり × | あり × | 33,000円(税込) | 無料~16,500円(税込) |
不要 ○ |
あり ○ | 詳細 |
×
優遇条件について
優遇条件がない場合、条件なく、表示金利で融資を受けることができます。
優遇条件がある場合、融資の優遇条件として「その銀行の預金口座を給与振込口座にする」「クレジットカードを作る」「投資口座を作る」などが必要 になります。
| 固定金利ならこちらの金融機関がおすすめ |
| 名称 | 金利 | 事務手数料 | 保証料 | 来店 | 金利 優遇条件 |
繰上げ 返済 |
詳細 | ||||
| フラット35 | フラット35S | ||||||||||
| 15年以上~20年以下 | 21年以上~35年以下 | 当初5年 | 6~10年目 | 11年目以降 | |||||||
 住信SBIネット銀行フラット35 |
1.03% | 1.12% | 0.78% | 0.78% | 1.03% | 借入額の0.99%(税込)~ | なし | 不要 | なし | 無料 | 詳細 |
 楽天銀行フラット35 |
1.02% | 1.11% | 0.77% | 0.77% | 1.02% | 借入額の1.10% | なし | 要 | なし | 無料 | 詳細 |
 ARUHI |
1.02% | 1.11% | 0.77% | 0.77% | 1.02% | 借入額の2.0% | なし | 要 | なし | 無料 | 詳細 |